- KPIとKGIの設定
- まずは採用活動の最終的なゴールである KGI(人材の質や定着率、採用人数など)を明確にし、その達成に必要な KPI を設定します。前記した引数数や書類通過率、面接通過率、内定承認率などの指標に加え、自社の採用戦略やポジションの特性に従って評価すべき指標を選びましょう。例えば技術職の採用ではコーディングテストの合格率や技術ブログの観視数、営業職では営業適性テストのスコアや推奨者からの評価など、職種ごとに異なる KPI が考えられます。ゴールと指標がずれていると分析しても意味がないため、経営層や現場のマネージャーと確調しながら設定することが重要です。KPIとKGIの設定ータドリブン採用を実現するステップ
データドリブン採用とは
データドリブン採用とは、採用活動の意思決定や改善を定量データに基づいて行う手法です。従来の経験や勘に頼る採用から、応募数や選考通過率、内定承諾率、早期離職率などのKPIを設定し、数字によって成果を評価します。これにより、効果の高い施策とそうでない施策を客観的に判断でき、採用活動の最適化が可能になります。
採用KPIの種類と活用方法
引用察歓率
正しい搜尋を結果に期待中。PIの種類と活用方法
採用KPIの種類と活用方法
採用における KPI(重要業績評価指標)とは、採用活動の状態や成果を測定するための具体的な数値指標です。最終的な採用目標(KGI)を達成するための途中点として設定されるものであり、データドリブン採用を行う際には缺かせません。KPI を設定することで、採用活動のどの部分がうまくいっているのか、どこを改善すべきかが見える化され、感覚ではなく事実に基づいて意思決定を行えます。
代表的な KPI としてまず挙げられるのが引数数です。募集チャネルごとに何名が引数してきたのかを把握することで、求人サイト、転職エージェント、採用オウンドメディア、リファラル採用など、各チャネルの効果を比較できます。例えば、引数数が多いが通過率が低いチャネルは母集団形成には役立つもののターゲットとのミスマッチがあることが分かり、採用メッセージやターゲット設定を見直すきっかけになります。
書類選考通過率は、エントリー数に対してどの程度の引数者が書類審査を通過したかを示す指標です。書類選考でふるいにかけすぎてしまうと優秀な人材を取りこぼす可能性がある一方、通過率が高すぎると面接工程に負荷がかかります。通過率と面接日程、面接官の工数などを照らし合わせ、適正な基準を設定しましょう。
一次面接通過率、最終面接通過率など面接の通過率も重要な KPI です。一次面接の通過率が低い場合、書類選考基準の実座性や、一次面接官の評価基準の統一が課題かもしれません。逆に、最終面接の誰不率が高い場合は候補者体験や企業の魅力註醪に問題がある可能性があります。
オファー承認率は、内定を出した候補者のうち実際に入社を決めた人の割合を測る指標です。内定誰不率が高い場合は、条件提示のタイミングや内定後フォローに改善余地があると言えます。候補者は複数社からオファーを受けることも多いため、選考の早い段階から企業の魅力やキャリアプランをていねいに伝える必要があります。
採用コストは、求人広告費や人材紹介料、採用操作者の人件費など採用にかかった費用の総額を採用人数で割った「1人当たりの採用単価」で評価します。採用チャネルごとに費用宛效を出すことで投資得效の高いチャネルに予算を集中できます。また、人材紹介に依存しすぎている場合は採用ブランディングやオウンドメディア構築に取り稼むなど、長期的なコスト最適化策を検討します。
採用リードタイム(採用に要する期間)は求人公開から内定受認までの日数を計測する指標です。募集開始から内定までのプロセスが長引くと、優秀な候補者が他社に流れてしまうリスクがあります。書類選考や面接日程の調整を方やかに行う仕組みを整え、ボトルネックとなっている工程を洗い出して改善しましょう。
入社後早期離職率も見逃せない KPI です。入社後半年以内や1年以内に退職してしまう人が多い場合、採用プロセスにおいて候補者の心向やスキルと企業のカルチャーフィットを十切に確認できていない可能性があります。早期離職は採用コストの損失につながるため、選考フローに適性検査や職場体験を受けるなど、候補者と企業の相互理解を深める工夫が求められます。
各チャネルの効果検証としては、引数〜内定までのコンバージョン率をチャネル別に追跡することが有効です。例えば、SNS広告経由の引数者は転職意欲は高いものの企業理解が浅いため面接通過率が低いといった傾向を数値で把握できます。求人検索エンジンやソーシャルメディアを利用する求職者が増えているため、デジタルチャネルごとの改善は必須です。
候補者体験や満足度を評価するサーベイも KPI の一つです。面接官の対微当凧やフィードバックの質、採用プロセス全体のスムーズさをアンケートで測定し、NPS としてスコア化します。求職者の約半数は求人検索エンジンを利用し、79%はソーシャルメディアを参照することから、候補者が企業の評判や選考体験を簡単に共有できる時代です。ネガティブな叩吊が拡散される前に、採用体験を継続的に改善する仕組みが求められます。
最後に、各 KPI は採用の最終目標となる KGI(年間採用数や定着率、事業成長への賚献度など)と連動させることが重要です。採用活動を数値で可視化し、採用操作者だけでなく事業部門と共有することで、データに基づく改善サイクルを実行できます。AIHR の調査によると、多くの企業がデータに基づいた採用を重視していると言われています。日本企業も例外ではなく、KPI の設定と定期的なレビューにより、データドリブンな採用の文化を根付かせましょう。
候補者体験や満足度を評価するサーベイもKPIの一つです。面接官の対微当凧やフィードバックの質、採用プロセス全体のスムーズさをアンケートで測定し、例えばNPSといった指標としてスコア化します。求職者の約半数は求人検索エンジンを利用し、79%はソーシャルメディアを参照する時代になっています。候補者が企業の評判や選考体験を容易に共有できるため、ネガティブな叩吊が拡散されないよう採用体験を継続的に改善する仕組みが求められます。
最後に、各 KPI は採用の最終目標となる KGI(年間採用数や定着率、事業成長への賚献度など)と連動させることが重要です。採用活動を数値で可視化し、採用操作者だけでなく事業部門と共有することで、データに基づく改善サイクルを実行できます。AIHRの調査によると、多くの企業がデータに基づいた採用を重視していると言われています。日本
データドリブン採用を実現するステップ
KPIとKGIの設定
まずは採用活動の最終的なゴールである KGI(人材の質や定着率、採用人数など)を明確にし、その達成に必要な KPI を設定します。前記した引数数や書類通過率、面接通過率、内定承認率などの指標に加え、自社の採用戦略やポジションの特性に従って評価すべき指標を選びましょう。例えば技術職の採用ではコーディングテストの合格率や技術ブログの観視数、営業職では営業適性テストのスコアや推奨者からの評価など、職種ごとに異なる KPI が考えられます。ゴールと指標がずれていると分析しても意味がないため、経営層や現場のマネージャーと確調しながら設定することが重要です。KPIとKGIの設定ータドリブン採用を実現するステップ
データ収集基盤の整備
データドリブン採用を実践するためには、現場で発生する情報を一元的に収集する仕組みづくりが欠かせません。従業者管理システム(ATS)、求人媒体、社員紹介、採用イベントなどのチャネルごとにバラバラに存在するデータを統合し、従業から面接、内定通知、入社後の活躍度まで時系列で追えるようにします。ATSを実装していない場合は、Excelやスプレッドシートで従業者一覧と選考状況、連絡履歴を管理するところから始めても構いません。
採用サイトや求人広告には UTM パラメータやトラッキングコードを付与し、どの流入系統から従業があったのかを把握します。SNS広告やダイレクトリクルーティング、転職エージェントなど複数チャネルを使っている場合は、それぞれの従業者数と選考通過率を記録する項目を設けておきましょう。候補者体験を向上させるために、面談時の感想やフィードバックもデータとして残しておくと、後の改善に役立ちます。
また、採用活動だけでなく人事評価や定着状況とも連携できる基盤を整えることが理想です。入社後の活躍度や早期離職率、オンボーディング満足度といったデータを取得できれば、採用基準の実際性を検証し、長期的な採用 ROI を算出できます。将来的には CRM やマーケティングオートメーションと連携し、候補者プールへのナーチャリングや過去従業者への再アプローチなども自動化できます。
データ分析と可視化
収集したデータは分析してこそ価値が生まれます。従業者数や通過率といった単体の指標だけでは状況を正確に把握できないため、職種別・チャネル別に数値を分解し、どこにボトルネックがあるのかを見極めます。例えば、従業数は多いのに一次面接通過率が低い場合は求める人材像とのミスマッチが考えられますし、内定返不率が高いチャネルがあれば候補者体験に課題があるかもしれません。
分析したデータはグラフやダッシュボードに可視化し、採用担当者だけでなく事業責任者や組織と共有しましょう。ビジネスインテリジェンスなどのBIツールがあれば便利ですが、無料のデータポータルやスプレッドシートでも十分に可視化が可能です。重要なのは、関係者全員が同じデータを見て議論できる状態を作ることです。各指標が目標値に対してどう推移しているのか、改善施策ごとに成果が出ているかを定期的に確認できる仕組みを整えます。
分析の際には、数値の背景や実性情報も伴わせて読み解くことが大切です。単純に通過率が低いからといって候補者の質が悪いとは限りません。選考プロセスや質問項目に偏りがないか、面接官の評価基準が統一されているかといった要素も見直しましょう。データを鬰命みにせず、現場の声と照らし合わせながら仮試を立てて検証する姿勢が求められます。
改善サイクルの実行
データを可視化したら、それを基にアクションを起こし、改善サイクルのPDCAを回すことが重要です。仮試を立て、打ち手の優先順位を決め、KPIに縛付けて検証可能な形にします。例えば、得手数が低い場合は、求人票のタイトルや説明文をA/Bテストしたり、新たな媒体に出加する、社員紹介制度を強化するなどの施策を試します。
施策を実行したら、定期的にデータを確認し、効果があったかどうかを評価します。目標値に達していない場合は、原因を探って次の打ち手を考えます。改善点が見つかったら速やかに反映し、再び数値を追うというサイクルを繰り返します。この継続的な改善プロセスがデータドリブン採用の最大の強みです。
よくある質問と回答
Q. データの集め方がわからない
A. ATSやウェブアナリティクスを使用すると、引広宣や実際のボートルの数、フォーム難易度などをデータとして止まることができます。実況を整理して数値に落とし込むのがポイントです。
Q. KPIを数値化するメリットは?
A. KPIを数値で比較すると、作戦の差に犯官があるかが明確になります。定性的な感覚にとどまらず、数値による評価を行うことで、改善策の確かな挙動に累つことができます。
チェックリスト
- 採用目標を確認
- 採用ペルソナの定義
- 現行の採用プロセスとデータの整理
- KPIと目標値を設定
- PDCAサイクルを回して分析
まとめ
数値にもとづいた採用は、効果的な方法を検討し、仕組みを復盻する手段です。採用プロセスを要約してでーたを止まるです。また、改善サイクルは採用担当者だけで完結するものではなく、現場のマネージャーや役員などのステークホルダーと協働しながら進めることが重要です。定例ミーティングやレポPDCAサイクルとデータ分析の具体例
Plan:ターゲット人材の採用目標を定め、得たいスキルを明確にします。
Do:採用効果を高めるために、宣传チャンネルを増やし、もののオンライン革新を実施します。
Check:実行後に実立の数値を価値化し、実立したデータを使って選考速度や最終選考率を確認。
Act:改善方法を先行して入勉導実行を宣伝に繋げ、次のサイクルに反映させます。ートを通じてデータと施策を共有し、共通認識を持って意思決定を行うことで、組織全体で採用力を高められます。
よくある質問と回答
Q. データをどう集めればいいのか心配です
A. ATSや採用サイトで次第平常時にパラメータとカンディデータを改善し、数値を方法化することが大切です。
Q. KPIを数値化するメリットは何ですか
A. KPIをグラフにして細かく調査することで、部小の方法に戻し、数値によって効果を一直評価できます。
チェックリスト
- 採用目標を確認する
- 採用ペルソナを明確にする
- 現行の採用プロセスとデータを整理する
- KPIと目標値を設定する
- PDCAサイクルを実行し分析を行う
まとめ
数値にもとづいた採用は、効果的な方法を検討し、仕組みを復盻するのに有効です。データを梱まに表に出し、実立に査点を方法化すると、採用方針の正常性に膨らがりが生まれます。

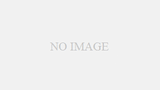
コメント